e
乮俇乯50cc悽奅慖庤尃傪妉摼乮徍榓37擭乯
丂墦惇寁夋傕敿偽偱嵙愜偟偨徍榓36擭(1961)丄偦偺晄怳偺偳傫掙偱丄俁夞栚偺挧愴寁夋偑棫偰傜傟偨丅36擭偺曢傟偵丄梻擭偐傜偼50cc偑怴偟偔悽奅慖庤尃儗乕僗偵壛偊傜傟傞偙偲偑寛掕偟偨丅偙傟偵婎偯偄偰丄50cc丄125cc丄250cc俁庬栚弌応傪栚昗偵偟偨弨旛偑巒傔傜傟偨丅惓寧媥傒偼傕偪傠傫曉忋偱偁傞丅丂
丂奜恖儔僀僟乕偵偼丄婸偐偟偄愴愌偺偁傞僨僌僫乕偑怴偨偵壛傢偭偰丄傾儞僟乕僜儞丄儁儕僗丄擔杮恖儔僀僟乕偲偟偰偼埳摗岝晇丄巗栰嶰愮梇丄楅栘惤堦乮忛杒儔僀僟乕僗乯丄怷壓孧偲丄嫮椡儊儞僶乕傪慻傫偱徍榓37擭(1962)偺僔乕僘儞傪寎偊偨丅
丂枮傪帩偟偰椪傫偩僗儁僀儞偺戞侾愴丄懕偄偰偺僼儔儞僗偺戞俀愴偲傕丄愴愌偼傑偨偟偰傕朏偟偔側偔丄125cc丄250cc偼巚傢偸僩儔僽儖偱姰憱傕巚偆偵傑偐偣偸桳條偱偁偭偨丅50cc係戜丄125cc俁戜丄250cc俁戜偺弌応幵偵懳偟偰丄儊僇僯僢僋偼傢偢偐偵俁柤偱丄僩儔僽儖偺偨傔揙栭偺楢懕偲側偭偨丅偙傟偱偼儊僇僯僢僋傪嶦偟偰偟傑偆偲丄幮挿偵揹曬傪懪偭偰丄乽250cc偺嶲壛偼庢傝巭傔傞乿偲偺嫋壜傪傕傜偆堦枊傕偁偭偨丅
丂偙偆偟偰儗乕僗僠乕儉偺嬯摤偑懕偄偰偄傞娫偵丄杮幮偱偼昁巰偺弌椡傾僢僾幚尡偑峴傢傟丄偮偄偵50cc偺戝暆側弌椡傾僢僾偵惉岟偟偨丅俿俿儗乕僗岞幃楙廗傕拞斦偲側偭偨俆寧28擔丄怴僄儞僕儞丄怴儅僼儔乕偑尰抧偵摓拝偟偨丅儊僇僯僢僋傕媣偟傇傝偵徫婄傪尒偣偰僄儞僕儞偺嵹偣姺偊偑巒傑偭偨丅29擔丄30擔丄懕偄偰俇寧俀擔偺岞幃楙廗傪捠偠偰丄僨僌僫乕偼30暘42昩俇偺岞幃僞僀儉偱侾埵偲側傝丄擮婅偺弶桪彑傕柌偱偼側偔側偭偨丅
丂俇寧俉擔偺摉擔偵側傞偲儅儞搰偼夣惏偵宐傑傟偰愨岲偺儗乕僗擔榓偲側偭偨丅屵慜10帪30暘丄僂僅乕儈儞僌傾僢僾傪奐巒偟偨33戜偺50cc儗乕僒乕偺攔婥壒偑丄搰偺嬻婥傪梙傞偑偣偨丅傗偑偰11帪偪傚偆偳丄幵斣俀偺僨僌僫乕乮僗僘僉乯偑塻偔敪恑偟偨丅10昩抶傟偰儈儞僞乕乮儂儞僟乯偲巗栰嶰愮梇乮僗僘僉乯丄偝傜偵懕偄偰10昩崗傒偵丄搰嶈乮儂儞僟乯偲傾儞僔儍僀僩乮僋儔僀僪儔乕乯丄儘僽乮儂儞僟乯丄僎乕僩儕僢僸乮僋儔僀僪儔乕乯偲僞儀儕乮儂儞僟乯丄僔儑乕儗僀乮僋儔僀僪儔乕乯偲埳摗岝晇乮僗僘僉)ゥゥゥ侾暘40昩抶傟偰楅栘惤堦乮僗僘僉乯偲丄懕乆偲僗僞乕僩偑愗傜傟偨丅儅儞搰俿俿儗乕僗偱偼丄偙偺傛偆偵10昩崗傒偵俀戜偢偮偑幵斣弴偵僗僞乕僩偡傞丅
丂僗僞乕僩偐傜32km抧揰偺僒儖價乕僽儕僢僕偱偼丄愭摢偼僨僌僫乕偩丅僗僞乕僩帪嵎傪擖傟偰傕丄俀埵僞儀儕乮儂儞僟乯偵俋昩偺嵎傪偮偗偰偄傞丅儗乕僗偼傗偑偰戞侾廃偐傜戞俀廃偵擖偭偨丅僩僢僾偼埶慠僨僌僫乕偱丄埲壓僗僞乕僩帪嵎傪廋惓偟偨弴埵偼丄俀埵僞儀儕丄俁埵儘僽丄係埵傾儞僔儍僀僩丄俆埵巗栰丄俇埵埳摗丄俋埵偵俿俿儗乕僗弶弌応偺楅栘惤堦偲偄偆弴偱偁傞丅僞儀儕丄儘僽偺儂儞僟惃偵15乣16昩偺嵎傪偮偗偰偄偨僨僌僫乕偼丄傑偡傑偡岲挷偱丄俀埵偲偺嵎偼偝傜偵峀偑傞偽偐傝偱偁傞丅
丂偮偄偵僑乕儖丅僨僌僫乕偼傕偺偡偛偄僗僺乕僪偱旘傃崬傫偱偒偨丅俀埵偲偺嵎偼傑偝偵18昩丄暥嬪側偟偺彑棙偱偁傞丅搑拞堦搙傕懠幵偺儕乕僪傪嫋偡偙偲側偔丄婲暁偲僇乕僽偺懡偄擄僐乕僗傪丄僗僞乕僩偐傜僑乕儖傑偱憱傝懕偗偨偺偱偁傞丅僨僌僫乕偺俀廃栚偺儔僢僾僞僀儉偼29暘58昩俇丄暯嬒帪懍121.54km丄俀廃偺儗乕僗僞僀儉偼60暘16昩係丄暯嬒帪懍120.9km丅乽弶傔偰峴傢傟偨50cc儗乕僗偼丄乭怣偢傋偐傜偞傞乭乭塕偺傛偆側乭乭嬃偔傋偒乭僗僺乕僪偺婰榐偱廔椆偟偨乿偲奺帍偼曬偠偨丅
丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂儗乕僗慜廻幧偺慜掚偱丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俆侽們們丂僗僞乕僩捈慜丄愭摢偺嘇偼桪彑偟偨僨僌僫乕丂丂丂丂侾俋俇俀擭俆侽們們儊乕僇乕慖庤尃妉摼
丂俿俿儗乕僗偺挿偄楌巎傪捠偠偰丄俀僒僀僋儖丒儗乕僒乕偺桪彑偼丄1938擭僪僀僣偺俢俲倂250埲棃側偐偭偨丅偟偨偑偭偰乽偙偺尩偟偄儅儞搰偱偼俀僗僩儘乕僋丒僄儞僕儞偼彑偮偙偲偑偱偒側偄乿偲偄偆偙偲偑丄偄偮偺娫偵偐僕儞僋僗偲側偭偰偄偨丅僗僘僉偼偙偺僕儞僋僗傪攋偭偨丅偟偐傕尒帠側乭慡偔怣偢傋偐傜偞傞乭婰榐偱桪彑偟偨偺偱偁傞丅
丂俿俿儗乕僗偱偺偙偺彑棙偼丄儔僀僟乕丄媄弍堳偵愨戝偺帺怣傪梌偊丄僆儔儞僟丄儀儖僊乕丄惣僪僀僣偲丄師乆偵峴傢傟偨儗乕僗偱傕丄埑搢揑側楢彑傪廂傔偨丅偦偟偰嵟廔愴傾儖僛儞僠儞偱偼偮偄偵擮婅偺50cc僋儔僗偺儊乕僇乕慖庤尃傪寛掕偟丄屄恖慖庤尃傕僨僌僫乕偺庤拞偵廂傔傜傟偨偺偱偁傞丅
丂偨偩丄惣僪僀僣偺屻偺傾儖僗僞乕GP125cc偱僨僌僫乕偑揮搢晧彎偟偰搶僪僀僣丄僀僞儕傾偲弌応偱偒偢丄慖庤尃偺峴曽傪弰偭偰椻娋傪偐偔巚偄傪偟偨偙偲偑偁傞丅搶僪僀僣偺儗乕僗偐傜丄僨僌僫乕偵戙傢偭偰戝暱偺傾儞僟乕僜儞偑婲梡偝傟偨偺偱偁偭偨丅斵偑傛偔38擭(1963)偲39擭(1964)偺50cc僠儍儞僺僆儞傪妉摼偡傞偙偲傪丄摉帪梊憐偟偨幰偼偄側偐偭偨丅
丂125cc丄250cc偼丄惈擻柺偱偼廩暘桪彑傪憟偊傞幵偱偁傝側偑傜丄埨掕惈偵寚偗偨偨傔偵岲惉愌傪巆偡偙偲偑偱偒側偐偭偨丅
丂側偍崙撪偱偼丄偙偺擭俋寧丄変偑崙偱弶傔偰偺姰慡曑憰偺儗乕僗丒僐乕僗楅幁僒乕僉僢僩偑姰惉偟丄11寧俁乣係椉擔丄戞侾夞慡擔杮慖庤尃儘乕僪儗乕僗偑惙戝偵嵜偝傟偨丅
丂50cc儗乕僗偱丄弶傔僨僌僫乕偑撈憱懺惃偵偁傝側偑傜係廃栚偱揮搢丄懕偄偰僩僢僾偵桇傝弌偨巗栰偑妝彑傪巚傢偣偨偑丄偙傟傑偨嵟廔儔僢僾偱揮搢偟偰桪彑偼儂儞僟偺儘僽偵扗傢傟偨丅偟偐偟丄俀丄俁丄係埵偵偼丄傾儞僟乕僜儞丄怷壓孧丄楅栘惤堦偲丄偄偢傟傕僗僘僉偑擖徿偟丄幚椡偺掱傪尒偣偨丅
丂125cc儗乕僗偼丄僗僘僉丄儂儞僟丄儎儅僴丄僩乕僴僣偺寛愴偲側偭偨丅埨掕惈傪憹偟偨僗僘僉125cc偼丄傛偔儂儞僟偵怘偄壓偑偭偰丄俀埵偵儁儕僗丄俇埵偵墇栰偑擖徿偟偨丅38擭搙(1963)偵側偭偰戝妶桇偡傞俀婥摏125cc偺帋嶌幵乮RT63X乯偵偼丄傾儞僟乕僜儞偑忔偭偰弌応偟偨丅
乮俈乯嵟戝偺惙傝忋偑傝傪尒偣偨儗乕僗乮徍榓38擭乯
丂慜擭枛偺楅幁偺儗乕僗偱125cc偵傕帺怣傪帩偰傞傛偆偵側傝丄戝暆偵惈擻傪岦忋偝傟偨50cc偵壛偊偰丄慜擭怴偟偔奐敪偝傟偨俀婥摏125cc傪弨旛偟偰丄1963擭俧俹儗乕僗偵挧傒丄慡儗乕僗傪捠偠偰堦斣戝偒側榖戣偲側偭偨丅弌応儔僀僟乕偼丄僨僌僫乕丄傾儞僟乕僜儞丄儁儕僗丄埳摗岝晇丄怷壓丄巗栰偵僆乕僗僩儕傾偺怴恑僔儏僫僀僟乕偑壛傢偭偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂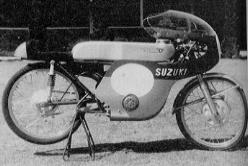 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俼俵俇俁丂俆侽們們丂儗乕僒乕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俼俿俇俁丂侾俀俆們們丂儗乕僒乕
丂125cc偼丄戞侾愴偺僗儁僀儞偙偦丄僩儔僽儖傗揮搢偱慡幵棊屴偺斶塣傪偐偙偭偨偑丄戞俀愴偺惣僪僀僣偐傜戞俋愴偺僼傿儞儔儞僪傑偱丄攋抾偺惃偄偱俉楢彑傪悑偘丄戞俉愴偺搶僪僀僣偱丄憗偔傕儊乕僇乕慖庤尃丄傾儞僟乕僜儞偺屄恖慖庤尃偑寛掕偟偨丅
丂俿俿儗乕僗偱傕丄侾埵傾儞僟乕僜儞丄俀埵儁儕僗丄俁埵僨僌僫乕丄俆埵僔儏僫僀僟乕丄偲僗僘僉偼埑搢揑側彑棙傪廂傔偨丅
丂50cc僋儔僗偼丄僗儁僀儞丄僼儔儞僗丄僼傿儞儔儞僪偱偼丄僋儔僀僪儔乕偺僄乕僗丄傾儞僔儍僀僩偵攕傟偼偟偨傕偺偺丄拝幚偵彑棙傪廳偹丄傾儖僛儞僠儞偱俀擭楢懕偺儊乕僇乕慖庤尃傪妉摼偟偨丅偙傟傪廽偭偰丄10寧係擔丄昹徏巗柉懱堢娰偵慡幮堳丄戙棟揦丄嫤椡岺応丄曬摴娭學幰偦偺懠懡偔偺恖乆偑廤傑偭偰丄俀擭楢懕儊乕僇乕慖庤尃妉摼廽夑夛偑惙戝偵嵜偝傟偨丅屄恖慖庤尃偼嵟廔偺擔杮俧俹傑偱帩偪墇偝傟偨偑丄寢嬊125cc摨條丄傾儞僟乕僜儞偵寛傑傝丄傾儞僟乕僜儞偼50cc丄125cc偺僟僽儖僞僀僩儖傪妉摼偟偨丅
丂TT儗乕僗50cc偱偼丄儗乕僗屻敿傑偱僨僌僫乕丄埳摗丄傾儞僟乕僜儞偺弴埵偱丄125cc偲摨條偵侾丄俀丄俁埵傪傕撈愯偡傞偐偲巚傢傟偨偑丄僨僌僫乕偺僩儔僽儖儕僞僀儎乕偺偨傔丄桪彑埳摗岝晇丄俀埵傾儞僟乕僜儞丄係埵怷壓丄俆埵巗栰偲側偭偨丅埳摗偺桪彑偼丄TT儗乕僗偵偍偄偰擔杮恖偲偟偰弶偺桪彑偱丄儅儞搰偺嬻崅偔丄弶傔偰偺擔復婙傪傂傞偑偊偟偨丅堎崙偺嬻偵崅乆偲擔復婙偑宖偘傜傟丄彑棙傪廽暉偡傞孨偑戙偺儊儘僨傿乕偑棳傟傞偺傪丄儊僇僯僢僋堦摨偼枩姶偺巚偄偱暦偄偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儅儞搰偱偺昞彶幃乮拞墰偼楅栘弐嶰幮挿乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俇寧侾係擔俀侾帪俀侽暘埳摗岝晇桪彑偺崙嵺揹榖偑庣塹強偵擖偭偨
丂偦傟傑偱偄偄抦傟偸嬯楯偵栙乆偲懴偊丄栚棫偨側偄搘椡傪廳偹偰偒偨寢壥偑偙偺擔偺惏傟偺塰岝偲側偭偰曬偄傜傟偨偺偱偁傞丅婌傃傪偠偭偲嫻偵姎傒掲傔側偑傜丄偝傜偵崱屻偺僗僘僉偺桇恑傪惥偄崌偭偨偺偱偁偭偨丅儀儖僊乕偱傕怷壓偑桪彑偟偰丄擔偺娵偑宖偘傜傟偨丅偙傟傜偺彑棙偺惉壥偵懳偟丄儗乕僗抍偍傛傃尋媶嶰壽偵幮挿昞彶偑峴傢傟偨丅
丂嵟廔愴偺擔杮俧俹儗乕僗偱偼丄50cc僋儔僗偱儂儞僟偺怴奐敪偺俀婥摏偵忔偭偨僞儀儕偵嬯攖傪媔偟偰丄俀丄俁丄係丄俆丄俇埵偲側偭偨丅125cc僋儔僗偼丄偙傟傕儂儞僟偺怴奐敪偺係婥摏儗乕僒乕偲僨僢僪僸乕僩傪揥奐偟偨偁偘偔丄傌儕僗偺戝妶桇偱桪彑偟偨丅250cc僋儔僗偵偼悽奅偱弶傔偰偺俀僒僀僋儖悈椻係婥摏傪弶弌応偝偣偨偑僨僌僫乕偑僗僞乕僩捈屻揮搢偟丄儗乕僒乕偼墛忋丄僨僌僫乕傕婄柺偵戝壩彎傪晧偭偨丅偙偺偨傔僨僌僫乕偼丄偦偺屻侾擭娫丄儗乕僗偐傜墦偞偐傞偙偲偵側偭偰偟傑偭偨丅
乮俉乯俁擭楢懕偺50cc僞僀僩儖傪妉摼乮徍榓39擭乯
丂徍榓39擭偺悽奅慖庤尃儗乕僗偵偼丄50cc丄125cc偺僞僀僩儖偺楢懕妉摼傪慱偆偙偲偼傕偪傠傫丄250cc偱傕僞僀僩儖傪妉摼偡傞偙偲傪栚巜偟偰丄嶲壛偟偨丅
丂50cc僋儔僗偼丄慜擭偺擔杮俧俹偵弶搊応偟偨儂儞僟偺俀婥摏偲丄傾儞僔儍僀僩傪梚偡傞僋儔僀僪儔乕偲偺嶰偮攂偺愙愴偲側偨偑丄傾儞僟乕僜儞偺戝妶桇偱俁擭楢懕儊乕僇乕慖庤尃傪妉摼偡傞偙偲偑偱偒偨丅傾儞僟乕僜儞偼俀擭楢懕偟偰偺屄恖慖庤尃傕庤偵擖傟偨偺偱偁傞丅
丂俿俿儗乕僗偱偼丄慜擭偵堷偒懕偄偰偺楢懕桪彑傪慱偆埳摗岝晇偑丄岞幃楙廗僞僀儉偱偼侾埵丅懕偄偰僽儔僀傾儞僘乮儂儞僟乯丄傾儞僟乕僜儞乮僗僘僉乯丄怷壓乮僗僘僉乯偺弴偱偁偭偨丅偄傛偄傛杮儗乕僗奐巒丄戞侾廃偺弴埵偼傾儞僟乕僜儞丄埳摗丄傾儞僔儍僀僩偱丄傾儞僟乕僜儞偲傾儞僔儍僀僩偺嵎偼9.2昩丅俀廃栚偵擖偭偰埳摗偺僗僺乕僪偑棊偪丄傾儞僟乕僜儞丄傾儞僔儍僀僩丄墇栰乮僗僘僉乯丄埳摗偺弴偲側偭偨丅俁廃栚偵擖傞偲僽儔僀傾儞僘乮儂儞僟乯偑傕偺偡偛偄捛偄崬傒傪尒偣丄俀埵偵忋偑偭偰丄傾儞僟乕僜儞乮僗僘僉乯丄僽儔僀傾儞僘乮儂儞僟乯丄怷壓乮僗僘僉乯丄傾儞僔儍僀僩乮僋儔僀僪儔乕乯丄埳摗乮僗僘僉乯丄扟岥乮儂儞僟乯偺弴偱僑乕儖僀儞偟偨丅埳摗偺俀擭楢懕桪彑偺柌偼攋傟偨偑丄傾儞僟乕僜儞偺夣憱傇傝偼尒帠偱丄僗僘僉偵俀擭楢懕偺桪彑傪傕偨傜偟偨丅儅儞搰弶弌応側偑傜傛偔寬摤偟偨墇栰偼丄俁廃栚偵惿偟偔傕揮搢儕僞僀傾乕偟偨丅嵟廔偺擔杮俧俹偵偼丄慖庤尃偑寛掕偝傟偨屻偱傕偁傝丄弌応傪拞巭偟偨丅
丂125們們僋儔僗偼丄惈擻柺偱偼寛偟偰堷偗傪偲傜側偄帺怣偑偁偭偨偑丄僉儍僽儗僞乕僩儔僽儖偵擸傑偝傟丄俿俿儗乕僗偱傕慡幵棊屴偲偄偆丄嶴傔側寢壥偲側偭偨丅僔乕僘儞屻敿偵側偭偰丄搶僪僀僣丄傾儖僗僞乕俧俹偵偼桪彑偟偨傕偺偺丄帪偡偱偵抶偔丄僞僀僩儖偼儂儞僟係婥摏偵扗傢傟偰偟傑偭偨丅
丂嵟廔偺擔杮俧俹偵偼丄怴奐敪偺悈椻俀婥摏儅僔儞傪弶搊応偝偣丄儂儞僟係婥摏偲偺懳寛偲側偭偨丅儗乕僗偼僐乕僗傪20廃丄侾廃栚偐傜傾儞僟乕僜儞偑僩僢僾傪愗偭偰丄偦偺傑傑桪彑側傞偐偲巚傢傟偨偑丄15廃栚偵側偭偰僩儔僽儖偱棊屴偟偰偟傑偭偨丅戙傢偭偰丄僗僞乕僩偼埆偐偭偨偑丄偠傝偠傝偲捛偄忋偘偰棃偨僨僌僫乕偑丄15廃栚偱僩僢僾偵恑弌偟丄捛偄偡偑傞僞儀儕乮儂儞僟乯傪戅偗偰桪彑偟偨丅僨僌僫乕偼慜擭擔杮俧俹偱偺壩彎偱侾擭娫寚応偟偰偄偨偺偩偑丄婏愓揑側僇儉僶僢僋傇傝偱偁偭偨丅偙偺擔杮俧俹偐傜偼傾儅僠儏傾丒儔僀僟乕偺曅嶳媊旤傕僗僘僉僠乕儉偵壛傢傝丄弶弌応偱俁埵偵擖徿偟偰婥傪揻偄偨丅
丂250們們偼丄戝攏椡傪屩傝側偑傜丄悈椻係婥摏偺偨傔廳検偑戝偒偔憖廲惈偵擄偑偁傝丄儅僔儞偺埨掕惈偵傕寚偗傞偲偙傠偑偁偭偰丄僼儔儞僗俧俹偱偺俁埵擖徿偑嵟崅偺惉愌偲偄偆丄婜懸奜傟偺惉愌偱偁偭偨丅250cc偵偼丄寉検僋儔僗偵愱擮偟偨偄偲偄偆傾儞僟乕僜儞偵戙傢偭偰丄僆乕僗僩儔儕傾偺儀僥儔儞慖庤丄俰丏傾僴乕儞偑婲梡偝傟丄僼儔儞僗俧俹丄俿俿儗乕僗I儔儞僟俧俹偵弌応偟偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儌乕僞乕僔儑乕偱俼俿俇俁儗乕僒乕傪偛棗偵側傞峜懢巕揳壓
乮俋乯嵞傃125們們偺僞僀僩儖妉摼乮徍榓40擭乯
丂50們們僋儔僗偱丄徍榓37丄38丄39擭偺俁夞偵傢偨傝僗僘僉偲僞僀僩儖傪憟偭偨惣僪僀僣偺柤栧僋儔僀僪儔乕偑丄徍榓40擭偐傜堷戅偡傞偙偲偵側偭偨偺偱丄偙偺擭偼儂儞僟俀婥摏偲丄38擭(1963)偐傜奐敪偑恑傔傜傟偰偄偨僗僘僉悈椻俀婥摏RK65偲偺娫偱寖偟偄慖庤尃憟偄偑峴傢傟傞偙偲偵側偭偨丅
丂偦偺寢壥偼丄傾儊儕僇丄僗儁僀儞丄儀儖僊乕偺奺儗乕僗偱偼僗僘僉丄惣僪僀僣丄僼儔儞僗丄俿俿儗乕僗丄僆儔儞僟偼儂儞僟丄偲桪彑傪暘偐偪崌偭偰儊乕僇乕慖庤尃丄屄恖慖庤尃偲傕丄嵟廔偺擔杮俧俹偵帩偪墇偝傟偨丅俿俿儗乕僗偱偼丄埳摗岝晇偑戞侾廃傪侾埵偱憱傝側偑傜丄僩儔僽儖偱儕僞僀儎乕傪梋媀側偔偝傟偨偺偼丄旕忢偵惿偟傑傟傞偙偲偱偁偭偨丅
丂慖庤尃傪偐偗偨 擔杮俧俹偼丄僗僘僉偺摗堜晀梇丄儂儞僟偺僞儀儕丄僽儔僀傾儞僘丄埲忋俁恖偺僩僢僾憟偄偵巒傑偭偨偑丄摗堜偼俇廃栚偵惿偟偔傕揮搢棊屴偟偨丅儗乕僗屻敿偵側偭偰偦傟傑偱柭傝傪愽傔偰偄偨傾儞僟乕僜儞偑捛偄忋偘傪尒偣丄偮偄偵嵟廔儔僢僾偵僩僢僾偵棫偭偨丅偟偐偟丄偦傟傕偮偐偺娫偱揮搢偟丄係擭楢懕儊乕僇乕慖庤尃偺柌偼徚偊嫀偭偨丅側偍丄偙偺擔杮俧俹偐傜偼丄尦僋儔僀僪儔乕偺僄乕僗丄傾儞僔儍僀僩偑僗僘僉僠乕儉偵壛傢傝丄係埵偵擖徿偟偨丅
丂125cc偼丄慜擭偺擔杮俧俹偵弶搊応偟偨悈椻俀婥摏偺惈擻傪峏偵岦忋偝偣偰帺怣枮乆偱儗乕僗偵椪傫偩丅傾儊儕僇丄惣僪僀僣丄僗儁僀儞丄僼儔儞僗偺奺儗乕僗偵弌応偟偰埑搢揑側係楢彑傪悑偘丄俿俿儗乕僗傪寎偊偨丅岞幃楙廗偱偼丄僨僌僫乕丄傾儞僟乕僜儞丄儕乕僪乮儎儅僴乯丄僞儀儕乮儂儞僟乯偺弴偱丄僗僘僉桳棙偺懺惃偱偁偭偨丅侾廃栚拞娫抧揰偱偼丄傾儞僟乕僜儞偑俀埵儕乕僪傪10昩堷偒棧偟偰僩僢僾偵棫偪丄撈憱偐偲巚傢偣偨偑丄偦偺屻僾儔僌僩儔僽儖偱岎姺偺偨傔10埵偵棊偪偰偟傑偭偨丅屻偼夣憱傪懕偗偰嵟崅儔僢僾僞僀儉傪婰榐偟偨偑丄寢壥偼戞俆埵偱廔傢偭偨丅50cc偺埳摗摨條丄晄塣側儗乕僗偲偄偆傋偒偱偁偭偨丅
丂偟偐偟丄屻敿愴偵擖偭偰丄搶僪僀僣丄僠僃僐丄傾儖僗僞乕丄僼傿儞儔儞僪丄僀僞儕傾偺奺儗乕僗偵楢彑偟丄僠僃僐俧俹偱憗偔傕儊乕僇乕慖庤尃傪寛掕偟偨丅屄恖慖庤尃偼丄傾儞僟乕僜儞偑徍榓38擭(1963)偵懕偄偰妉摼偟偨丅嵟廔偺擔杮俧俹偱偼丄怴搊応偺儂儞僟俆婥摏偲偺愙愴偵側偭偨偑丄傾儞僟乕僜儞偑寑揑側媡揮彑偪傪廂傔偨丅
丂250cc僋儔僗偼丄曅嶳丄儁儕僗丄傾僴乕儞偺恮梕偱慜敿愴偵弌応偟偨丅慜擭偵斾偟偰儅僔儞偺埨掕惈偼夵椙偝傟丄俿俿儗乕僗偱儁儕僗偑俁埵偵擖徿偟偨偑慖庤尃傪憟偆傑偱偵偼帄傜偢丄偙偺擭傪嵟屻偵儗乕僗奅偐傜巔傪徚偡偙偲偵側偭偨丅
乮侾侽乯傾儞僔儍僀僩丄50cc悽奅慖庤尃妉摼乮徍榓41擭乯
丂50cc僋儔僗偱丄慜擭幐偭偨僞僀僩儖偺扗娨傪栚巜偟偰丄惈擻傪戝暆偵岦忋偝偣偨悈椻俀婥摏RK66傪弌応偝偣偨偑丄儂儞僟俀婥摏偲愙愴傪墘偠偨屻丄巆擮側偑傜嵞傃儂儞僟偵慖庤尃傪忳偭偨丅丂
丂俿俿儗乕僗偱偼丄彉斦愴偱傾儞僟乕僜儞偑丄僞儀儕丄僽儔僀傾儞僘偺儂儞僟惃傪梷偊偰偄偨偑丄僄儞僕儞晄挷偲側傝桪彑傪堩偟丄偙偺偨傔僞僀僩儖傪堩偟偨偺偱偁傞丅嵟廔偺擔杮俧俹偼晉巑僗僺乕僪僂僃乕偱奐偐傟偨丅偡偱偵僞僀僩儖傪寛掕偟偨儂儞僟偼嶲壛偣偢丄俛俽偲偺憟偄偵側偭偨丅偙偺儗乕僗偱偼僗僘僉偑侾丄俀丄俁丄係埵傪撈愯偟丄侾埵偼曅嶳偱丄擔杮俧俹弶偺擔復婙偑宖偘傜傟偨偺偱偁傞丅傑偨屄恖慖庤尃偼怴宊栺偺傾儞僔儍僀僩偺摢忋偵婸偄偨偺偑丄偣傔偰傕偺堅傔偱偁偭偨丅
丂125cc僋儔僗偺慖庤尃偼丄儂儞僟偺俆婥摏丄怴恑儎儅僴偺悈椻俀婥摏丄僗僘僉偺悈椻俀婥摏偺娫偱憟傢傟傞偙偲偵側偭偨偑丄僗僘僉偼恑嫬偺挊偟偄曅嶳偺妶桇偵偐偐傢傜偢丄慡儗乕僗傪捠偠偰桪彑側偟偲偄偆晄挷偵廔傢偭偨丅奐敪偺恑傔傜傟偰偄偨悈椻俁婥摏媦傃悈椻係婥摏偺姰惉偑抶傟偨偙偲偑丄庡側攕場偱偁偭偨丅
乮侾侾乯係搙栚偺50cc僋儔僗慖庤尃偺妉摼乮徍榓42擭乯
丂徍榓41擭(1966)偺僔乕僘儞傪嵟屻偵丄傾儞僟乕僜儞丄僨僌僫乕丄儁儕僗偑堷戅偟偨偺偱丄徍榓42擭(1967)儗乕僗偼丄曅嶳媊旤丄傾儞僔儍僀僩偵壛偊偰丄怴壛擖偺俽丏僌儔僴儉偺俁柤傪庡幉偲偡傞僠乕儉偱僞僀僩儖偵挧愴偟偨丅
丂50cc僋儔僗偼丄儂儞僟偑晄嶲壛偺偨傔丄僗儁僀儞偺僨儖價傪憡庤偵偡傞偙偲偵側傝丄慡彑傪忺偭偨丅偙傟偱俁擭怳傝係搙栚偺儊乕僇乕慖庤尃傪妉摼偟丄屄恖慖庤尃傕丄慜擭偵堷偒懕偄偰傾儞僔儍僀僩偺庤拞偵廂傔傜傟偨丅嵟廔偺擔杮俧俹偱偼儀僥儔儞埳摗岝晇偑摪乆桪彑偟丄慜擭偺曅嶳偵懕偄偰擔復婙傪宖偘偨丅
丂125cc僋儔僗偼丄戝暆偵惈擻傪崅傔偨悈椻俀婥摏RT67嘦宆偱帺怣傪帩偭偰俧俹儗乕僗偺奐枊傪寎偊丄怴搊応偺儎儅僴悈椻係婥摏偲僞僀僩儖傪憟偆偙偲偵側偭偨偑丄曅嶳丄僌儔僴儉偺慞愴偑偁偭偨偵傕偐偐傢傜偢丄惣僪僀僣偲僼傿儞儔儞僪偱桪彑偟偨偩偗偱丄僞僀僩儖偼儎儅僴偵扗傢傟偰偟傑偭偨丅俿俿儗乕僗偱偼僌儔僴儉偲儕乕僪乮儎儅僴乯偺娫偱敳偒偮敳偐傟偮偺戝愙愴偑揥奐偝傟偨枛丄傢偢偐3.4昩偺嵎偱惿偟偔傕俀埵偵側偭偨丅嵟廔偺擔杮俧俹偱偼丄姰惉側偭偨悈椻係婥摏RS67嘦宆傪弶搊応偝偣丄帺怣枮乆偲偟偰昁彑傪婜偟偨偑丄僄乕僗曅嶳偑楙廗拞揮搢晧彎偟偰弌応偱偒偢丄僌儔僴儉偺寬摤嬻偟偔丄俀埵偵娒傫偠偨丅
乮侾俀乯俧俹儗乕僗奅偐傜堷戅乮徍榓43擭乯
丂僗僘僉偼偙傟傑偱偵婸偐偟偄愴壥傪廂傔丄僗僘僉偺柤惡傪慡悽奅偵崅傔偰丄俧俹儗乕僗嶲壛偺弶婜偺栚揑傪払偟偨偺偱丄偙偺擭(1968)偐傜俧俹儗乕僗奅偐傜堷戅偡傞偙偲傪寛掕偟丄俉擭娫懕偄偨悽奅慖庤尃偺挧愴偵廔巭晞傪懪偭偨丅偙偺偨傔偡偱偵奐敪偝傟偰偄偨50cc悈椻俁婥摏傕丄偮偄偵俧俹儗乕僗偵巔傪尰偡僠儍儞僗傪摼側偐偭偨丅
丂偟偐偟丄50cc僋儔僗偼丄慜擭搙儗乕僒乕傪傾儞僔儍僀僩偵戄梌偟偰丄屄恖弌応偱僞僀僩儖偵挧愴偡傞偙偲偵側偭偨丅傾儞僔儍僀僩偼俆愴拞係儗乕僗偵弌応丄桪彑俁夞丄俀埵侾夞偲偄偆岲惉愌傪忋偘丄俁擭楢懕偺屄恖慖庤尃傪妉摼偡傞偲偲傕偵丄儊乕僇乕慖庤尃傪僗僘僉偵傕偨傜偟偨丅丂
丂偙傟傑偱弎傋偰偒偨傛偆偵丄慜屻俉擭娫偵傢偨偭偰懕偗傜傟偨俧俹儗乕僗偺嶲壛偼丄僗僘僉偵壗傪傕偨傜偟偨偱偁傠偆偐丅
丂傑偢丄僄儞僕儞傪堦偮偺嬻婥婡夿偲峫偊丄扨埵帪娫偵傛傝懡偔偺嬻婥傪媧偄崬傒丄偦偺偆偪偺傛傝懡偔偺妱崌傪擱從偝偣傞曽朄乮偙傟偑弌椡岦忋媄弍偱偁傞偑乯傪巒傔丄僋儔儞僋幒埑弅斾偺寛掕朄媦傃攔婥娗岠壥偺媄弍傪懱摼偡傞偙偲偑偱偒偨丅傑偨丄埨掕惈丒懴媣惈岦忋懳嶔偲偟偰丄傾儖儈僔儕儞僟乕偵拻揝僗儕乕僽從偽傔偁傞偄偼梟拝丄偝傜偵崅懍夞揮偵懴偊傞僯乕僪儖儀傾儕儞僌偺奐敪側偳丄儗乕僒乕奐敪偱摼偨宱尡偲媄弍偼丄偦偺傑傑偱丄偁傞偄偼偦偺峫偊曽偑捈愙彜昳偵摫擖偝傟丄懡戝偺惉壥傪忋偘傞偙偲偑偱偒偨丅
丂堦曽丄偦傟偲摨帪偵丄悽奅俧俹儗乕僗偱偼埑搢揑側嫮偝傪敪婗偟偨偨傔偐丄儌乕僞乕僗億乕僣偲偟偰偺寬慡惈偵媈栤傪書偐偣傞傛偆側暤埻婥偑惗偠巒傔偨偙偲傕斲掕偱偒偢丄偙偺帪婜偵柤梍偁傞廔巭晞傪懪偭偨偙偲偼丄帪媂傪摼偨傕偺偱偁偭偨偲偄偆偙偲偑偱偒傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偦偺侾傊丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂Menu 傊
丂墦惇寁夋傕敿偽偱嵙愜偟偨徍榓36擭(1961)丄偦偺晄怳偺偳傫掙偱丄俁夞栚偺挧愴寁夋偑棫偰傜傟偨丅36擭偺曢傟偵丄梻擭偐傜偼50cc偑怴偟偔悽奅慖庤尃儗乕僗偵壛偊傜傟傞偙偲偑寛掕偟偨丅偙傟偵婎偯偄偰丄50cc丄125cc丄250cc俁庬栚弌応傪栚昗偵偟偨弨旛偑巒傔傜傟偨丅惓寧媥傒偼傕偪傠傫曉忋偱偁傞丅丂
丂奜恖儔僀僟乕偵偼丄婸偐偟偄愴愌偺偁傞僨僌僫乕偑怴偨偵壛傢偭偰丄傾儞僟乕僜儞丄儁儕僗丄擔杮恖儔僀僟乕偲偟偰偼埳摗岝晇丄巗栰嶰愮梇丄楅栘惤堦乮忛杒儔僀僟乕僗乯丄怷壓孧偲丄嫮椡儊儞僶乕傪慻傫偱徍榓37擭(1962)偺僔乕僘儞傪寎偊偨丅
丂枮傪帩偟偰椪傫偩僗儁僀儞偺戞侾愴丄懕偄偰偺僼儔儞僗偺戞俀愴偲傕丄愴愌偼傑偨偟偰傕朏偟偔側偔丄125cc丄250cc偼巚傢偸僩儔僽儖偱姰憱傕巚偆偵傑偐偣偸桳條偱偁偭偨丅50cc係戜丄125cc俁戜丄250cc俁戜偺弌応幵偵懳偟偰丄儊僇僯僢僋偼傢偢偐偵俁柤偱丄僩儔僽儖偺偨傔揙栭偺楢懕偲側偭偨丅偙傟偱偼儊僇僯僢僋傪嶦偟偰偟傑偆偲丄幮挿偵揹曬傪懪偭偰丄乽250cc偺嶲壛偼庢傝巭傔傞乿偲偺嫋壜傪傕傜偆堦枊傕偁偭偨丅
丂偙偆偟偰儗乕僗僠乕儉偺嬯摤偑懕偄偰偄傞娫偵丄杮幮偱偼昁巰偺弌椡傾僢僾幚尡偑峴傢傟丄偮偄偵50cc偺戝暆側弌椡傾僢僾偵惉岟偟偨丅俿俿儗乕僗岞幃楙廗傕拞斦偲側偭偨俆寧28擔丄怴僄儞僕儞丄怴儅僼儔乕偑尰抧偵摓拝偟偨丅儊僇僯僢僋傕媣偟傇傝偵徫婄傪尒偣偰僄儞僕儞偺嵹偣姺偊偑巒傑偭偨丅29擔丄30擔丄懕偄偰俇寧俀擔偺岞幃楙廗傪捠偠偰丄僨僌僫乕偼30暘42昩俇偺岞幃僞僀儉偱侾埵偲側傝丄擮婅偺弶桪彑傕柌偱偼側偔側偭偨丅
丂俇寧俉擔偺摉擔偵側傞偲儅儞搰偼夣惏偵宐傑傟偰愨岲偺儗乕僗擔榓偲側偭偨丅屵慜10帪30暘丄僂僅乕儈儞僌傾僢僾傪奐巒偟偨33戜偺50cc儗乕僒乕偺攔婥壒偑丄搰偺嬻婥傪梙傞偑偣偨丅傗偑偰11帪偪傚偆偳丄幵斣俀偺僨僌僫乕乮僗僘僉乯偑塻偔敪恑偟偨丅10昩抶傟偰儈儞僞乕乮儂儞僟乯偲巗栰嶰愮梇乮僗僘僉乯丄偝傜偵懕偄偰10昩崗傒偵丄搰嶈乮儂儞僟乯偲傾儞僔儍僀僩乮僋儔僀僪儔乕乯丄儘僽乮儂儞僟乯丄僎乕僩儕僢僸乮僋儔僀僪儔乕乯偲僞儀儕乮儂儞僟乯丄僔儑乕儗僀乮僋儔僀僪儔乕乯偲埳摗岝晇乮僗僘僉)ゥゥゥ侾暘40昩抶傟偰楅栘惤堦乮僗僘僉乯偲丄懕乆偲僗僞乕僩偑愗傜傟偨丅儅儞搰俿俿儗乕僗偱偼丄偙偺傛偆偵10昩崗傒偵俀戜偢偮偑幵斣弴偵僗僞乕僩偡傞丅
丂僗僞乕僩偐傜32km抧揰偺僒儖價乕僽儕僢僕偱偼丄愭摢偼僨僌僫乕偩丅僗僞乕僩帪嵎傪擖傟偰傕丄俀埵僞儀儕乮儂儞僟乯偵俋昩偺嵎傪偮偗偰偄傞丅儗乕僗偼傗偑偰戞侾廃偐傜戞俀廃偵擖偭偨丅僩僢僾偼埶慠僨僌僫乕偱丄埲壓僗僞乕僩帪嵎傪廋惓偟偨弴埵偼丄俀埵僞儀儕丄俁埵儘僽丄係埵傾儞僔儍僀僩丄俆埵巗栰丄俇埵埳摗丄俋埵偵俿俿儗乕僗弶弌応偺楅栘惤堦偲偄偆弴偱偁傞丅僞儀儕丄儘僽偺儂儞僟惃偵15乣16昩偺嵎傪偮偗偰偄偨僨僌僫乕偼丄傑偡傑偡岲挷偱丄俀埵偲偺嵎偼偝傜偵峀偑傞偽偐傝偱偁傞丅
丂偮偄偵僑乕儖丅僨僌僫乕偼傕偺偡偛偄僗僺乕僪偱旘傃崬傫偱偒偨丅俀埵偲偺嵎偼傑偝偵18昩丄暥嬪側偟偺彑棙偱偁傞丅搑拞堦搙傕懠幵偺儕乕僪傪嫋偡偙偲側偔丄婲暁偲僇乕僽偺懡偄擄僐乕僗傪丄僗僞乕僩偐傜僑乕儖傑偱憱傝懕偗偨偺偱偁傞丅僨僌僫乕偺俀廃栚偺儔僢僾僞僀儉偼29暘58昩俇丄暯嬒帪懍121.54km丄俀廃偺儗乕僗僞僀儉偼60暘16昩係丄暯嬒帪懍120.9km丅乽弶傔偰峴傢傟偨50cc儗乕僗偼丄乭怣偢傋偐傜偞傞乭乭塕偺傛偆側乭乭嬃偔傋偒乭僗僺乕僪偺婰榐偱廔椆偟偨乿偲奺帍偼曬偠偨丅
丂丂丂丂
 丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂儗乕僗慜廻幧偺慜掚偱丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俆侽們們丂僗僞乕僩捈慜丄愭摢偺嘇偼桪彑偟偨僨僌僫乕丂丂丂丂侾俋俇俀擭俆侽們們儊乕僇乕慖庤尃妉摼
丂俿俿儗乕僗偺挿偄楌巎傪捠偠偰丄俀僒僀僋儖丒儗乕僒乕偺桪彑偼丄1938擭僪僀僣偺俢俲倂250埲棃側偐偭偨丅偟偨偑偭偰乽偙偺尩偟偄儅儞搰偱偼俀僗僩儘乕僋丒僄儞僕儞偼彑偮偙偲偑偱偒側偄乿偲偄偆偙偲偑丄偄偮偺娫偵偐僕儞僋僗偲側偭偰偄偨丅僗僘僉偼偙偺僕儞僋僗傪攋偭偨丅偟偐傕尒帠側乭慡偔怣偢傋偐傜偞傞乭婰榐偱桪彑偟偨偺偱偁傞丅
丂俿俿儗乕僗偱偺偙偺彑棙偼丄儔僀僟乕丄媄弍堳偵愨戝偺帺怣傪梌偊丄僆儔儞僟丄儀儖僊乕丄惣僪僀僣偲丄師乆偵峴傢傟偨儗乕僗偱傕丄埑搢揑側楢彑傪廂傔偨丅偦偟偰嵟廔愴傾儖僛儞僠儞偱偼偮偄偵擮婅偺50cc僋儔僗偺儊乕僇乕慖庤尃傪寛掕偟丄屄恖慖庤尃傕僨僌僫乕偺庤拞偵廂傔傜傟偨偺偱偁傞丅
丂偨偩丄惣僪僀僣偺屻偺傾儖僗僞乕GP125cc偱僨僌僫乕偑揮搢晧彎偟偰搶僪僀僣丄僀僞儕傾偲弌応偱偒偢丄慖庤尃偺峴曽傪弰偭偰椻娋傪偐偔巚偄傪偟偨偙偲偑偁傞丅搶僪僀僣偺儗乕僗偐傜丄僨僌僫乕偵戙傢偭偰戝暱偺傾儞僟乕僜儞偑婲梡偝傟偨偺偱偁偭偨丅斵偑傛偔38擭(1963)偲39擭(1964)偺50cc僠儍儞僺僆儞傪妉摼偡傞偙偲傪丄摉帪梊憐偟偨幰偼偄側偐偭偨丅
丂125cc丄250cc偼丄惈擻柺偱偼廩暘桪彑傪憟偊傞幵偱偁傝側偑傜丄埨掕惈偵寚偗偨偨傔偵岲惉愌傪巆偡偙偲偑偱偒側偐偭偨丅
丂側偍崙撪偱偼丄偙偺擭俋寧丄変偑崙偱弶傔偰偺姰慡曑憰偺儗乕僗丒僐乕僗楅幁僒乕僉僢僩偑姰惉偟丄11寧俁乣係椉擔丄戞侾夞慡擔杮慖庤尃儘乕僪儗乕僗偑惙戝偵嵜偝傟偨丅
丂50cc儗乕僗偱丄弶傔僨僌僫乕偑撈憱懺惃偵偁傝側偑傜係廃栚偱揮搢丄懕偄偰僩僢僾偵桇傝弌偨巗栰偑妝彑傪巚傢偣偨偑丄偙傟傑偨嵟廔儔僢僾偱揮搢偟偰桪彑偼儂儞僟偺儘僽偵扗傢傟偨丅偟偐偟丄俀丄俁丄係埵偵偼丄傾儞僟乕僜儞丄怷壓孧丄楅栘惤堦偲丄偄偢傟傕僗僘僉偑擖徿偟丄幚椡偺掱傪尒偣偨丅
丂125cc儗乕僗偼丄僗僘僉丄儂儞僟丄儎儅僴丄僩乕僴僣偺寛愴偲側偭偨丅埨掕惈傪憹偟偨僗僘僉125cc偼丄傛偔儂儞僟偵怘偄壓偑偭偰丄俀埵偵儁儕僗丄俇埵偵墇栰偑擖徿偟偨丅38擭搙(1963)偵側偭偰戝妶桇偡傞俀婥摏125cc偺帋嶌幵乮RT63X乯偵偼丄傾儞僟乕僜儞偑忔偭偰弌応偟偨丅
乮俈乯嵟戝偺惙傝忋偑傝傪尒偣偨儗乕僗乮徍榓38擭乯
丂慜擭枛偺楅幁偺儗乕僗偱125cc偵傕帺怣傪帩偰傞傛偆偵側傝丄戝暆偵惈擻傪岦忋偝傟偨50cc偵壛偊偰丄慜擭怴偟偔奐敪偝傟偨俀婥摏125cc傪弨旛偟偰丄1963擭俧俹儗乕僗偵挧傒丄慡儗乕僗傪捠偠偰堦斣戝偒側榖戣偲側偭偨丅弌応儔僀僟乕偼丄僨僌僫乕丄傾儞僟乕僜儞丄儁儕僗丄埳摗岝晇丄怷壓丄巗栰偵僆乕僗僩儕傾偺怴恑僔儏僫僀僟乕偑壛傢偭偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂
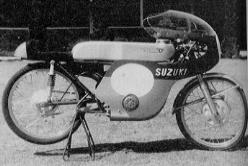 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俼俵俇俁丂俆侽們們丂儗乕僒乕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俼俿俇俁丂侾俀俆們們丂儗乕僒乕
丂125cc偼丄戞侾愴偺僗儁僀儞偙偦丄僩儔僽儖傗揮搢偱慡幵棊屴偺斶塣傪偐偙偭偨偑丄戞俀愴偺惣僪僀僣偐傜戞俋愴偺僼傿儞儔儞僪傑偱丄攋抾偺惃偄偱俉楢彑傪悑偘丄戞俉愴偺搶僪僀僣偱丄憗偔傕儊乕僇乕慖庤尃丄傾儞僟乕僜儞偺屄恖慖庤尃偑寛掕偟偨丅
丂俿俿儗乕僗偱傕丄侾埵傾儞僟乕僜儞丄俀埵儁儕僗丄俁埵僨僌僫乕丄俆埵僔儏僫僀僟乕丄偲僗僘僉偼埑搢揑側彑棙傪廂傔偨丅
丂50cc僋儔僗偼丄僗儁僀儞丄僼儔儞僗丄僼傿儞儔儞僪偱偼丄僋儔僀僪儔乕偺僄乕僗丄傾儞僔儍僀僩偵攕傟偼偟偨傕偺偺丄拝幚偵彑棙傪廳偹丄傾儖僛儞僠儞偱俀擭楢懕偺儊乕僇乕慖庤尃傪妉摼偟偨丅偙傟傪廽偭偰丄10寧係擔丄昹徏巗柉懱堢娰偵慡幮堳丄戙棟揦丄嫤椡岺応丄曬摴娭學幰偦偺懠懡偔偺恖乆偑廤傑偭偰丄俀擭楢懕儊乕僇乕慖庤尃妉摼廽夑夛偑惙戝偵嵜偝傟偨丅屄恖慖庤尃偼嵟廔偺擔杮俧俹傑偱帩偪墇偝傟偨偑丄寢嬊125cc摨條丄傾儞僟乕僜儞偵寛傑傝丄傾儞僟乕僜儞偼50cc丄125cc偺僟僽儖僞僀僩儖傪妉摼偟偨丅
丂TT儗乕僗50cc偱偼丄儗乕僗屻敿傑偱僨僌僫乕丄埳摗丄傾儞僟乕僜儞偺弴埵偱丄125cc偲摨條偵侾丄俀丄俁埵傪傕撈愯偡傞偐偲巚傢傟偨偑丄僨僌僫乕偺僩儔僽儖儕僞僀儎乕偺偨傔丄桪彑埳摗岝晇丄俀埵傾儞僟乕僜儞丄係埵怷壓丄俆埵巗栰偲側偭偨丅埳摗偺桪彑偼丄TT儗乕僗偵偍偄偰擔杮恖偲偟偰弶偺桪彑偱丄儅儞搰偺嬻崅偔丄弶傔偰偺擔復婙傪傂傞偑偊偟偨丅堎崙偺嬻偵崅乆偲擔復婙偑宖偘傜傟丄彑棙傪廽暉偡傞孨偑戙偺儊儘僨傿乕偑棳傟傞偺傪丄儊僇僯僢僋堦摨偼枩姶偺巚偄偱暦偄偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儅儞搰偱偺昞彶幃乮拞墰偼楅栘弐嶰幮挿乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俇寧侾係擔俀侾帪俀侽暘埳摗岝晇桪彑偺崙嵺揹榖偑庣塹強偵擖偭偨
丂偦傟傑偱偄偄抦傟偸嬯楯偵栙乆偲懴偊丄栚棫偨側偄搘椡傪廳偹偰偒偨寢壥偑偙偺擔偺惏傟偺塰岝偲側偭偰曬偄傜傟偨偺偱偁傞丅婌傃傪偠偭偲嫻偵姎傒掲傔側偑傜丄偝傜偵崱屻偺僗僘僉偺桇恑傪惥偄崌偭偨偺偱偁偭偨丅儀儖僊乕偱傕怷壓偑桪彑偟偰丄擔偺娵偑宖偘傜傟偨丅偙傟傜偺彑棙偺惉壥偵懳偟丄儗乕僗抍偍傛傃尋媶嶰壽偵幮挿昞彶偑峴傢傟偨丅
丂嵟廔愴偺擔杮俧俹儗乕僗偱偼丄50cc僋儔僗偱儂儞僟偺怴奐敪偺俀婥摏偵忔偭偨僞儀儕偵嬯攖傪媔偟偰丄俀丄俁丄係丄俆丄俇埵偲側偭偨丅125cc僋儔僗偼丄偙傟傕儂儞僟偺怴奐敪偺係婥摏儗乕僒乕偲僨僢僪僸乕僩傪揥奐偟偨偁偘偔丄傌儕僗偺戝妶桇偱桪彑偟偨丅250cc僋儔僗偵偼悽奅偱弶傔偰偺俀僒僀僋儖悈椻係婥摏傪弶弌応偝偣偨偑僨僌僫乕偑僗僞乕僩捈屻揮搢偟丄儗乕僒乕偼墛忋丄僨僌僫乕傕婄柺偵戝壩彎傪晧偭偨丅偙偺偨傔僨僌僫乕偼丄偦偺屻侾擭娫丄儗乕僗偐傜墦偞偐傞偙偲偵側偭偰偟傑偭偨丅
乮俉乯俁擭楢懕偺50cc僞僀僩儖傪妉摼乮徍榓39擭乯
丂徍榓39擭偺悽奅慖庤尃儗乕僗偵偼丄50cc丄125cc偺僞僀僩儖偺楢懕妉摼傪慱偆偙偲偼傕偪傠傫丄250cc偱傕僞僀僩儖傪妉摼偡傞偙偲傪栚巜偟偰丄嶲壛偟偨丅
丂50cc僋儔僗偼丄慜擭偺擔杮俧俹偵弶搊応偟偨儂儞僟偺俀婥摏偲丄傾儞僔儍僀僩傪梚偡傞僋儔僀僪儔乕偲偺嶰偮攂偺愙愴偲側偨偑丄傾儞僟乕僜儞偺戝妶桇偱俁擭楢懕儊乕僇乕慖庤尃傪妉摼偡傞偙偲偑偱偒偨丅傾儞僟乕僜儞偼俀擭楢懕偟偰偺屄恖慖庤尃傕庤偵擖傟偨偺偱偁傞丅
丂俿俿儗乕僗偱偼丄慜擭偵堷偒懕偄偰偺楢懕桪彑傪慱偆埳摗岝晇偑丄岞幃楙廗僞僀儉偱偼侾埵丅懕偄偰僽儔僀傾儞僘乮儂儞僟乯丄傾儞僟乕僜儞乮僗僘僉乯丄怷壓乮僗僘僉乯偺弴偱偁偭偨丅偄傛偄傛杮儗乕僗奐巒丄戞侾廃偺弴埵偼傾儞僟乕僜儞丄埳摗丄傾儞僔儍僀僩偱丄傾儞僟乕僜儞偲傾儞僔儍僀僩偺嵎偼9.2昩丅俀廃栚偵擖偭偰埳摗偺僗僺乕僪偑棊偪丄傾儞僟乕僜儞丄傾儞僔儍僀僩丄墇栰乮僗僘僉乯丄埳摗偺弴偲側偭偨丅俁廃栚偵擖傞偲僽儔僀傾儞僘乮儂儞僟乯偑傕偺偡偛偄捛偄崬傒傪尒偣丄俀埵偵忋偑偭偰丄傾儞僟乕僜儞乮僗僘僉乯丄僽儔僀傾儞僘乮儂儞僟乯丄怷壓乮僗僘僉乯丄傾儞僔儍僀僩乮僋儔僀僪儔乕乯丄埳摗乮僗僘僉乯丄扟岥乮儂儞僟乯偺弴偱僑乕儖僀儞偟偨丅埳摗偺俀擭楢懕桪彑偺柌偼攋傟偨偑丄傾儞僟乕僜儞偺夣憱傇傝偼尒帠偱丄僗僘僉偵俀擭楢懕偺桪彑傪傕偨傜偟偨丅儅儞搰弶弌応側偑傜傛偔寬摤偟偨墇栰偼丄俁廃栚偵惿偟偔傕揮搢儕僞僀傾乕偟偨丅嵟廔偺擔杮俧俹偵偼丄慖庤尃偑寛掕偝傟偨屻偱傕偁傝丄弌応傪拞巭偟偨丅
丂125們們僋儔僗偼丄惈擻柺偱偼寛偟偰堷偗傪偲傜側偄帺怣偑偁偭偨偑丄僉儍僽儗僞乕僩儔僽儖偵擸傑偝傟丄俿俿儗乕僗偱傕慡幵棊屴偲偄偆丄嶴傔側寢壥偲側偭偨丅僔乕僘儞屻敿偵側偭偰丄搶僪僀僣丄傾儖僗僞乕俧俹偵偼桪彑偟偨傕偺偺丄帪偡偱偵抶偔丄僞僀僩儖偼儂儞僟係婥摏偵扗傢傟偰偟傑偭偨丅
丂嵟廔偺擔杮俧俹偵偼丄怴奐敪偺悈椻俀婥摏儅僔儞傪弶搊応偝偣丄儂儞僟係婥摏偲偺懳寛偲側偭偨丅儗乕僗偼僐乕僗傪20廃丄侾廃栚偐傜傾儞僟乕僜儞偑僩僢僾傪愗偭偰丄偦偺傑傑桪彑側傞偐偲巚傢傟偨偑丄15廃栚偵側偭偰僩儔僽儖偱棊屴偟偰偟傑偭偨丅戙傢偭偰丄僗僞乕僩偼埆偐偭偨偑丄偠傝偠傝偲捛偄忋偘偰棃偨僨僌僫乕偑丄15廃栚偱僩僢僾偵恑弌偟丄捛偄偡偑傞僞儀儕乮儂儞僟乯傪戅偗偰桪彑偟偨丅僨僌僫乕偼慜擭擔杮俧俹偱偺壩彎偱侾擭娫寚応偟偰偄偨偺偩偑丄婏愓揑側僇儉僶僢僋傇傝偱偁偭偨丅偙偺擔杮俧俹偐傜偼傾儅僠儏傾丒儔僀僟乕偺曅嶳媊旤傕僗僘僉僠乕儉偵壛傢傝丄弶弌応偱俁埵偵擖徿偟偰婥傪揻偄偨丅
丂250們們偼丄戝攏椡傪屩傝側偑傜丄悈椻係婥摏偺偨傔廳検偑戝偒偔憖廲惈偵擄偑偁傝丄儅僔儞偺埨掕惈偵傕寚偗傞偲偙傠偑偁偭偰丄僼儔儞僗俧俹偱偺俁埵擖徿偑嵟崅偺惉愌偲偄偆丄婜懸奜傟偺惉愌偱偁偭偨丅250cc偵偼丄寉検僋儔僗偵愱擮偟偨偄偲偄偆傾儞僟乕僜儞偵戙傢偭偰丄僆乕僗僩儔儕傾偺儀僥儔儞慖庤丄俰丏傾僴乕儞偑婲梡偝傟丄僼儔儞僗俧俹丄俿俿儗乕僗I儔儞僟俧俹偵弌応偟偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儌乕僞乕僔儑乕偱俼俿俇俁儗乕僒乕傪偛棗偵側傞峜懢巕揳壓
乮俋乯嵞傃125們們偺僞僀僩儖妉摼乮徍榓40擭乯
丂50們們僋儔僗偱丄徍榓37丄38丄39擭偺俁夞偵傢偨傝僗僘僉偲僞僀僩儖傪憟偭偨惣僪僀僣偺柤栧僋儔僀僪儔乕偑丄徍榓40擭偐傜堷戅偡傞偙偲偵側偭偨偺偱丄偙偺擭偼儂儞僟俀婥摏偲丄38擭(1963)偐傜奐敪偑恑傔傜傟偰偄偨僗僘僉悈椻俀婥摏RK65偲偺娫偱寖偟偄慖庤尃憟偄偑峴傢傟傞偙偲偵側偭偨丅
丂偦偺寢壥偼丄傾儊儕僇丄僗儁僀儞丄儀儖僊乕偺奺儗乕僗偱偼僗僘僉丄惣僪僀僣丄僼儔儞僗丄俿俿儗乕僗丄僆儔儞僟偼儂儞僟丄偲桪彑傪暘偐偪崌偭偰儊乕僇乕慖庤尃丄屄恖慖庤尃偲傕丄嵟廔偺擔杮俧俹偵帩偪墇偝傟偨丅俿俿儗乕僗偱偼丄埳摗岝晇偑戞侾廃傪侾埵偱憱傝側偑傜丄僩儔僽儖偱儕僞僀儎乕傪梋媀側偔偝傟偨偺偼丄旕忢偵惿偟傑傟傞偙偲偱偁偭偨丅
丂慖庤尃傪偐偗偨 擔杮俧俹偼丄僗僘僉偺摗堜晀梇丄儂儞僟偺僞儀儕丄僽儔僀傾儞僘丄埲忋俁恖偺僩僢僾憟偄偵巒傑偭偨偑丄摗堜偼俇廃栚偵惿偟偔傕揮搢棊屴偟偨丅儗乕僗屻敿偵側偭偰偦傟傑偱柭傝傪愽傔偰偄偨傾儞僟乕僜儞偑捛偄忋偘傪尒偣丄偮偄偵嵟廔儔僢僾偵僩僢僾偵棫偭偨丅偟偐偟丄偦傟傕偮偐偺娫偱揮搢偟丄係擭楢懕儊乕僇乕慖庤尃偺柌偼徚偊嫀偭偨丅側偍丄偙偺擔杮俧俹偐傜偼丄尦僋儔僀僪儔乕偺僄乕僗丄傾儞僔儍僀僩偑僗僘僉僠乕儉偵壛傢傝丄係埵偵擖徿偟偨丅
丂125cc偼丄慜擭偺擔杮俧俹偵弶搊応偟偨悈椻俀婥摏偺惈擻傪峏偵岦忋偝偣偰帺怣枮乆偱儗乕僗偵椪傫偩丅傾儊儕僇丄惣僪僀僣丄僗儁僀儞丄僼儔儞僗偺奺儗乕僗偵弌応偟偰埑搢揑側係楢彑傪悑偘丄俿俿儗乕僗傪寎偊偨丅岞幃楙廗偱偼丄僨僌僫乕丄傾儞僟乕僜儞丄儕乕僪乮儎儅僴乯丄僞儀儕乮儂儞僟乯偺弴偱丄僗僘僉桳棙偺懺惃偱偁偭偨丅侾廃栚拞娫抧揰偱偼丄傾儞僟乕僜儞偑俀埵儕乕僪傪10昩堷偒棧偟偰僩僢僾偵棫偪丄撈憱偐偲巚傢偣偨偑丄偦偺屻僾儔僌僩儔僽儖偱岎姺偺偨傔10埵偵棊偪偰偟傑偭偨丅屻偼夣憱傪懕偗偰嵟崅儔僢僾僞僀儉傪婰榐偟偨偑丄寢壥偼戞俆埵偱廔傢偭偨丅50cc偺埳摗摨條丄晄塣側儗乕僗偲偄偆傋偒偱偁偭偨丅
丂偟偐偟丄屻敿愴偵擖偭偰丄搶僪僀僣丄僠僃僐丄傾儖僗僞乕丄僼傿儞儔儞僪丄僀僞儕傾偺奺儗乕僗偵楢彑偟丄僠僃僐俧俹偱憗偔傕儊乕僇乕慖庤尃傪寛掕偟偨丅屄恖慖庤尃偼丄傾儞僟乕僜儞偑徍榓38擭(1963)偵懕偄偰妉摼偟偨丅嵟廔偺擔杮俧俹偱偼丄怴搊応偺儂儞僟俆婥摏偲偺愙愴偵側偭偨偑丄傾儞僟乕僜儞偑寑揑側媡揮彑偪傪廂傔偨丅
丂250cc僋儔僗偼丄曅嶳丄儁儕僗丄傾僴乕儞偺恮梕偱慜敿愴偵弌応偟偨丅慜擭偵斾偟偰儅僔儞偺埨掕惈偼夵椙偝傟丄俿俿儗乕僗偱儁儕僗偑俁埵偵擖徿偟偨偑慖庤尃傪憟偆傑偱偵偼帄傜偢丄偙偺擭傪嵟屻偵儗乕僗奅偐傜巔傪徚偡偙偲偵側偭偨丅
乮侾侽乯傾儞僔儍僀僩丄50cc悽奅慖庤尃妉摼乮徍榓41擭乯
丂50cc僋儔僗偱丄慜擭幐偭偨僞僀僩儖偺扗娨傪栚巜偟偰丄惈擻傪戝暆偵岦忋偝偣偨悈椻俀婥摏RK66傪弌応偝偣偨偑丄儂儞僟俀婥摏偲愙愴傪墘偠偨屻丄巆擮側偑傜嵞傃儂儞僟偵慖庤尃傪忳偭偨丅丂
丂俿俿儗乕僗偱偼丄彉斦愴偱傾儞僟乕僜儞偑丄僞儀儕丄僽儔僀傾儞僘偺儂儞僟惃傪梷偊偰偄偨偑丄僄儞僕儞晄挷偲側傝桪彑傪堩偟丄偙偺偨傔僞僀僩儖傪堩偟偨偺偱偁傞丅嵟廔偺擔杮俧俹偼晉巑僗僺乕僪僂僃乕偱奐偐傟偨丅偡偱偵僞僀僩儖傪寛掕偟偨儂儞僟偼嶲壛偣偢丄俛俽偲偺憟偄偵側偭偨丅偙偺儗乕僗偱偼僗僘僉偑侾丄俀丄俁丄係埵傪撈愯偟丄侾埵偼曅嶳偱丄擔杮俧俹弶偺擔復婙偑宖偘傜傟偨偺偱偁傞丅傑偨屄恖慖庤尃偼怴宊栺偺傾儞僔儍僀僩偺摢忋偵婸偄偨偺偑丄偣傔偰傕偺堅傔偱偁偭偨丅
丂125cc僋儔僗偺慖庤尃偼丄儂儞僟偺俆婥摏丄怴恑儎儅僴偺悈椻俀婥摏丄僗僘僉偺悈椻俀婥摏偺娫偱憟傢傟傞偙偲偵側偭偨偑丄僗僘僉偼恑嫬偺挊偟偄曅嶳偺妶桇偵偐偐傢傜偢丄慡儗乕僗傪捠偠偰桪彑側偟偲偄偆晄挷偵廔傢偭偨丅奐敪偺恑傔傜傟偰偄偨悈椻俁婥摏媦傃悈椻係婥摏偺姰惉偑抶傟偨偙偲偑丄庡側攕場偱偁偭偨丅
乮侾侾乯係搙栚偺50cc僋儔僗慖庤尃偺妉摼乮徍榓42擭乯
丂徍榓41擭(1966)偺僔乕僘儞傪嵟屻偵丄傾儞僟乕僜儞丄僨僌僫乕丄儁儕僗偑堷戅偟偨偺偱丄徍榓42擭(1967)儗乕僗偼丄曅嶳媊旤丄傾儞僔儍僀僩偵壛偊偰丄怴壛擖偺俽丏僌儔僴儉偺俁柤傪庡幉偲偡傞僠乕儉偱僞僀僩儖偵挧愴偟偨丅
丂50cc僋儔僗偼丄儂儞僟偑晄嶲壛偺偨傔丄僗儁僀儞偺僨儖價傪憡庤偵偡傞偙偲偵側傝丄慡彑傪忺偭偨丅偙傟偱俁擭怳傝係搙栚偺儊乕僇乕慖庤尃傪妉摼偟丄屄恖慖庤尃傕丄慜擭偵堷偒懕偄偰傾儞僔儍僀僩偺庤拞偵廂傔傜傟偨丅嵟廔偺擔杮俧俹偱偼儀僥儔儞埳摗岝晇偑摪乆桪彑偟丄慜擭偺曅嶳偵懕偄偰擔復婙傪宖偘偨丅
丂125cc僋儔僗偼丄戝暆偵惈擻傪崅傔偨悈椻俀婥摏RT67嘦宆偱帺怣傪帩偭偰俧俹儗乕僗偺奐枊傪寎偊丄怴搊応偺儎儅僴悈椻係婥摏偲僞僀僩儖傪憟偆偙偲偵側偭偨偑丄曅嶳丄僌儔僴儉偺慞愴偑偁偭偨偵傕偐偐傢傜偢丄惣僪僀僣偲僼傿儞儔儞僪偱桪彑偟偨偩偗偱丄僞僀僩儖偼儎儅僴偵扗傢傟偰偟傑偭偨丅俿俿儗乕僗偱偼僌儔僴儉偲儕乕僪乮儎儅僴乯偺娫偱敳偒偮敳偐傟偮偺戝愙愴偑揥奐偝傟偨枛丄傢偢偐3.4昩偺嵎偱惿偟偔傕俀埵偵側偭偨丅嵟廔偺擔杮俧俹偱偼丄姰惉側偭偨悈椻係婥摏RS67嘦宆傪弶搊応偝偣丄帺怣枮乆偲偟偰昁彑傪婜偟偨偑丄僄乕僗曅嶳偑楙廗拞揮搢晧彎偟偰弌応偱偒偢丄僌儔僴儉偺寬摤嬻偟偔丄俀埵偵娒傫偠偨丅
乮侾俀乯俧俹儗乕僗奅偐傜堷戅乮徍榓43擭乯
丂僗僘僉偼偙傟傑偱偵婸偐偟偄愴壥傪廂傔丄僗僘僉偺柤惡傪慡悽奅偵崅傔偰丄俧俹儗乕僗嶲壛偺弶婜偺栚揑傪払偟偨偺偱丄偙偺擭(1968)偐傜俧俹儗乕僗奅偐傜堷戅偡傞偙偲傪寛掕偟丄俉擭娫懕偄偨悽奅慖庤尃偺挧愴偵廔巭晞傪懪偭偨丅偙偺偨傔偡偱偵奐敪偝傟偰偄偨50cc悈椻俁婥摏傕丄偮偄偵俧俹儗乕僗偵巔傪尰偡僠儍儞僗傪摼側偐偭偨丅
丂偟偐偟丄50cc僋儔僗偼丄慜擭搙儗乕僒乕傪傾儞僔儍僀僩偵戄梌偟偰丄屄恖弌応偱僞僀僩儖偵挧愴偡傞偙偲偵側偭偨丅傾儞僔儍僀僩偼俆愴拞係儗乕僗偵弌応丄桪彑俁夞丄俀埵侾夞偲偄偆岲惉愌傪忋偘丄俁擭楢懕偺屄恖慖庤尃傪妉摼偡傞偲偲傕偵丄儊乕僇乕慖庤尃傪僗僘僉偵傕偨傜偟偨丅丂
丂偙傟傑偱弎傋偰偒偨傛偆偵丄慜屻俉擭娫偵傢偨偭偰懕偗傜傟偨俧俹儗乕僗偺嶲壛偼丄僗僘僉偵壗傪傕偨傜偟偨偱偁傠偆偐丅
丂傑偢丄僄儞僕儞傪堦偮偺嬻婥婡夿偲峫偊丄扨埵帪娫偵傛傝懡偔偺嬻婥傪媧偄崬傒丄偦偺偆偪偺傛傝懡偔偺妱崌傪擱從偝偣傞曽朄乮偙傟偑弌椡岦忋媄弍偱偁傞偑乯傪巒傔丄僋儔儞僋幒埑弅斾偺寛掕朄媦傃攔婥娗岠壥偺媄弍傪懱摼偡傞偙偲偑偱偒偨丅傑偨丄埨掕惈丒懴媣惈岦忋懳嶔偲偟偰丄傾儖儈僔儕儞僟乕偵拻揝僗儕乕僽從偽傔偁傞偄偼梟拝丄偝傜偵崅懍夞揮偵懴偊傞僯乕僪儖儀傾儕儞僌偺奐敪側偳丄儗乕僒乕奐敪偱摼偨宱尡偲媄弍偼丄偦偺傑傑偱丄偁傞偄偼偦偺峫偊曽偑捈愙彜昳偵摫擖偝傟丄懡戝偺惉壥傪忋偘傞偙偲偑偱偒偨丅
丂堦曽丄偦傟偲摨帪偵丄悽奅俧俹儗乕僗偱偼埑搢揑側嫮偝傪敪婗偟偨偨傔偐丄儌乕僞乕僗億乕僣偲偟偰偺寬慡惈偵媈栤傪書偐偣傞傛偆側暤埻婥偑惗偠巒傔偨偙偲傕斲掕偱偒偢丄偙偺帪婜偵柤梍偁傞廔巭晞傪懪偭偨偙偲偼丄帪媂傪摼偨傕偺偱偁偭偨偲偄偆偙偲偑偱偒傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偦偺侾傊丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂Menu 傊