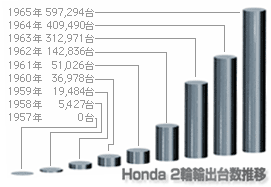|
|
|
||||||||||||

|
この時に痛いほど思い知ったのは、グランプリに出場するとは、レースで速い遅いはもちろん、その生活やレース環境を成り立たせ、日々の中に無限に発生してくる問題を解決していかなければならないという強烈なまでの現実だった。 パドックのどこにトランスポーターを停めれば良いか、電気や水道をどう上手く引っ張ってくるか、予定どおり供給されないタイヤをどうかすめ取ってくるか、在庫が無いというオイルをどこで調達してくるか、忙しく作業を続けるメンバーの食事をどう手配するか、寝床になるはずのキャンパーが借りられずトラックの荷台で寝るための段ボールをどこで探してくるか、計13個230kgの荷物のうちヘルメットとツナギの入ったバッグが届かず航空会社にかけあってレースに間に合わせるにはどうしたら良いか、書き出せばキリがないほどの問題が、毎日のボクの目前にあった。 |
|||
|
|||
|
マネージャー的立場の苦労として感嘆したものに、出発前の「渡航準備」という話があった。これは決して、マシンがなかなか完成しなかった…とか、レースへの参加費用が不足した…というものではない。当時の日本の状態を思わせる面白い逸話だった。 Hondaのマン島TT初挑戦の1959年当時、日本ではまだ海外旅行が自由化されておらず、海外渡航を許されるのは公的な外交官や、輸出によって外貨を獲得できるごく一部の商社/企業の社員などに限られていた。当時、輸出どころか海外から工作機械を買うばかりで外貨を使うことしか出来なかったHondaの社員に渡航許可がおりるはずもなく、やむなくHondaと工作機械の輸入で取引のある商社の嘱託社員になるというかたちで、メンバー全員の渡航許可がおりるという苦労があったという。 |
|||
 |
|||
|
その商社は、大倉商事という。ホテルの名などでも有名なその会社は、1873(明治6)年創業の大倉財閥系の商社で、明治7年には日本企業として初めてロンドンに海外支店を設置する進取の気風をもった会社だった。 イギリスに、ブルックランズという世界初のレース専用サーキットが開設されたのは1907年のこと(この年は、第1回マン島TTが開催された記念すべき年でもある)。このオープニングレースで2位に入賞したのが、大倉財閥二代目の大倉喜七郎という人物だった。そのレース参加が創業者の父に知れて日本に無理矢理連れ戻されるというオマケまで付くその人物は、間違いなく日本人として初めて海外のレースに参加した人物だった。 |
|||
|
|||
|
こうしてなんとか渡航許可がおりたものの、次に直面したのは「お金をいくら持っていけるか」という、今では考えられないような問題だった。当時、個人が持ち出せる外貨は1人500ドル(1ドル360円の為替レートの時代であり、約18万円)が上限だった。つまり、10人が渡航するとして、持って行けるお金は180万円にしかならない。約一ヶ月前からマン島に入って練習を始めようとするHondaチームにとって、そんな持ち金でレースを遂行することは完全に無理な話だった。 そこで登場するのが、当時20代だったHondaチームの敏腕マネージャー、飯田佳孝という人物だ。彼は大蔵省の為替管理課に日参し、度重なる折衝を繰り広げた。なぜHondaは海外のレースに参加するのか。海外のレースに参加して好成績をあげるとどうなるのか。いずれは輸出が増え、ひいては日本の外貨獲得に大きく貢献するであろうことを、彼は切々と説いたという。 はたして大蔵省のお役人様が、オートバイとかマン島とかRC142とか、その真意を理解出来たかどうかは分からないが、とにもかくにも最終的に飯田さんは必要なだけの額の持ち出し許可を得たというのだから、その情熱はすさまじいものだったのだろう。 |
|||
|
|||
| 後年、「マシンづくりより、ドルづくりの方が大変だった」という話を聞いたこともある。1959年のレーシングチームが海外のレースに参戦するというのは、それほど困難な作業だったのだ。いろんな立場で、いろんな方法で、いろんな局面で、チャレンジスピリットというものは発揮されるんだな…と、感心させられる話だった。 | |||
|
|
|||
 |
|||
|
60年代のHondaのGP初挑戦時には、もっと豪快でもっと巧妙な手が使われたという。なにしろ4ストロークエンジンにはサイレンサーが無く、ガバッとメガフォンマフラーが口を開けていた時代の話だ。深夜にエンジンをかけようものなら、それこそ大変な騒ぎになることは必至だった。 Hondaのメカニックたちはマシンが仕上がると、これをおもむろにトランスポーターに積み込み、宿を抜け出した。そして民家がとぎれる辺りまでトランポを走らせ、その中に固定したままのレーシングマシンのエンジンをかけた。トランポは走り続けたままだ。ドライバーとメカニックは耳栓をしていたと言うが、そのトランポの中の轟音たるや、想像を絶するものであっただろう。 こうすれば、エンジン音はかなり抑えることが出来る。そしてトランポが走り続けているかぎり、外に漏れる轟音が一定の場所に留まっていることもない。エンジンの順調な仕上がりを確認したメカニックは、明け方近くになって宿に戻り、つかの間の休息を得ようとした。しかし彼らの耳鳴りは止まず、眠ることすら出来なかったというのだから、凄い話だ。 このような豪快な話はレース界には幾つも残されているようだ。80年代、鈴鹿8時間耐久レースが急激に厳しさを増していく頃、某チームは深夜にマシンをトランポに積み込み、東名阪を目指した。そのチームが、60年代のHondaと同じ方法でエンジンの調子を見たのか、はたまた実際にレーシングマシンが東名阪を疾走してしまったのか、真偽のほどは定かではない。ひとつだけ言えることは「必要は発明の母である」という超現実だけなのかもしれない。 |
|||
|
|||
|
そしてこれを克服したのもHondaのメカニックの仕事だったというから痛快だ。ガスケットを吹き抜いて立ち往生した路端でガスケット紙を切り抜き、ヘッドを開けてこれを交換するという作業など造作もないことだったという。足周りに入ったクラックを溶接し、エンジンを修理し、欠損した部品を作り、彼らはヨーロッパ大陸を走り巡ってグランプリを戦った。 シーズンを終えて日本に持ち帰られたトランポが、これ以上ない実用耐久テストを果たし、弱点に補強を施し、改良まで加えられていたのは言うまでもない。N社の車両が、その頃急速に性能や耐久性、信頼性を向上させたかどうか、正式な資料は残されていないようだが…。 50〜60年代に、日本人が世界に挑むという裏には、事ほどさような苦労があったのは確かだ。マン島初挑戦で結果を期待されたライダーたちのひとりから「まるで特攻に行くような心境だった」という話を聞いた事がある。千人針こそ渡されなかっただろうが、ライダーたちの責任感や不安、そして燃えるような闘志は、ギリギリのものであったことは容易に想像がつく。 とは言うものの、今から考えれば珍妙な話もある。毎日トレーニングに励み、立てなくなるまでマシンに乗ったというライダーたちだが、彼らは練習走行を終えると、次なる厳しいトレーニングを消化しなければならなかった。 |
|||
|
|||
|
ちなみに日本では、1963年に業務渡航が自由化され、一般の海外旅行が自由化されたのは翌64年。ジャルパックが発売されて細々とながらも一般の海外旅行者が出始めたのは65年のことだった。それでも65年の海外渡航者は16万人。2000年の統計によれば日本から1780万人の人間が海外に飛び立っているというのだから、65年はその100分の1以下。マン島初挑戦の59年には恐らく数万人程度の日本人が海外におもむいたに過ぎないだろう。 1959年、昭和34年とは、そういう時代だったのである。 |
|||
|
59年のHondaによるマン島初挑戦で、レース結果の報告を行なうのも、マネージャー飯田さんの重要な役割だった。まず速報を国際電報によってHonda本社に打電し、同時に申し込んでおく国際電話が交換手を通じてつながるのが半日後という状態だった。この国際電話によって、河島監督の声が、雑音とディレイで切れ切れになりながら本田社長に伝えられたという。メールも携帯もない、昭和34年の話だ。 |
|||
|
|||
|
金融界の反応は驚くほど速く、Hondaのマン島初挑戦を高く評価していたのだから仰天せざるを得ない。現在、ロッシがチャンピオンを獲得して、Hondaの株価はどんな変化を見せるのだろうか。ちょっと興味もあり、また興味を持ってもしょうがないのかな…と思うこともある。 マン島初挑戦の3日後には、通産省から報道関係者宛に、Hondaのマン島挑戦に関する公式通知が行われた。この通知の中で「Hondaの戦績は一企業の業績であるが、国産2輪車がこれで世界水準に達し、日本製品の今後の輸出にも明るい見通しが立った」との評価がなされ、Hondaの名は日本の経済界全体に広がることとなった。レースで高性能を実証し市販車の販売に結びつけるという、レースに不変の価値は、マン島初出場の時点から大きな成果をあげていたことになる。 |
|||
|